近年、数多くの温浴施設で実施されているサービスであるロウリュ・アウフグース。ロウリュとは元々はフィンランド語で蒸気を意味し、アウフグースはドイツ式の入浴方法でロウリュして発生した蒸気をタオルで攪拌することを意味する。
日本においてはアウフグース自体をロウリュと表している施設も多く(本来のロウリュの意味とは違うが、それが正しいかどうかを議論するつもりはないため、ここでは触れないでおく)、今日では数多くの施設において人気のサービスになっている。日本で最初にロウリュサービスを始めたのは確か今は亡きスパプラザだったと聞いたことがあるが(間違っていたら申し訳ありません)、現在の日本におけるロウリュサービスでスタンダードなのはアロマ水をサウナストーンにかけることだろう。
アロマの芳しい香りがサウナ室全体へ広がり、心身ともにリフレッシュする気がするのは僕だけではないはずだ。ロウリュサービスの際に熱波師の方々がアロマの効能を口頭で紹介することが多いと思うが、その際によく聞く台詞として「〇〇というアロマには抗菌効果があります」という一文が挙げられる。
確かに芳しいアロマを全身で浴びると抗菌効果があるように感じられるが、果たしてロウリュの際のアロマ水には本当に抗菌効果があるのであろうか?今回は抗菌薬・抗ウイルス薬の作用機序などと比較してアロマ水の抗菌効果を紐解いていきたいと思う。
(注意:あくまで個人的な意見・見解であり、僕は完全に門外漢であるため、参考程度になれば幸いです)
まずアロマ水に抗菌・抗ウイルス効果があるかどうかを議論する前に細菌とウイルスの違いを説明していきたい。細菌は細胞壁を持つ原核生物の一つと定義され、ウイルスは細胞膜も持たないため自己増殖することがないため非生物とされるが、微生物学では両方とも微生物に分類される。わかりやすく言うと細菌は自ら栄養を摂取して単独で増殖出来るのに対し、ウイルスは単独では増殖できないため動物などの細胞内に侵入して増殖する。
要するに、細菌は自身の周りに餌となる栄養素さえあれば自分のDNAを複製・増殖することが出来る。その作用を利用したのが「発酵」のメカニズムであるのは多くの人がご存知だと思う。一方でウイルスは上記した通り単独では増殖できない。では、どうやって増殖していくのか?ウイルスは他の生物の細胞の中に入り込み、その細胞の持っているDNAやRNAの増殖機構を借りて増殖するのである。
この辺りはWikipediaでも調べて読んでいただくとわかりやすいため、詳しいことは割愛させて頂くが、ざっくりと言ってしまうと増殖する仕組み・細胞壁の有無など細菌とウイルスでは全く別物であるということだ。また、ウイルスは細菌よりも約50分の1と小さく、大きさも全く異なることが特徴である。

(赤血球と比較した細菌・ウイルスの大きさの違い。 http://amr.ncgm.go.jp/general/1-1-2.htmlより)
細菌とウイルスが全く別の“モノ”であることを記したわけだが、この違いによって抗菌薬・抗ウイルス薬の作用機序も変わってくる。まず抗菌薬に関してだが、現在では細胞壁合成阻害剤、細胞膜阻害剤、タンパク質合成阻害剤、核酸合成阻害剤など色々と作用機序が違う抗菌薬が販売されている。
まず、細胞壁合成阻害剤。細菌特有の細胞壁の合成を選択的に阻害することにより、細胞壁が壊れるので細菌が死滅するというメカニズムだ。細胞膜阻害剤も細胞壁阻害剤と似たような仕組みであり、細菌の細胞膜に直接作用して障害を引き起こし、細胞内成分を放出して死滅するというわけだ。
タンパク質合成阻害剤はタンパク質合成の場所であるリボゾーム(r-RNA)の機能に作用し、細菌のタンパク合成を阻害する。
最後に核酸合成阻害剤だが、細菌の複製を司るデオキシリボ核酸(DNA)やリボ核酸(RNA)の合成過程を阻害することにより、細菌のタンパク質合成が停止し、分裂・増殖が不可能になるため殺菌される。
それぞれの薬の持つ作用によって働きかける部分が違うというところが抗菌薬の一つのポイントであり、この作用機序が違うことによって薬の機能を評価する指標も違ってくるのが重要な部分だ。
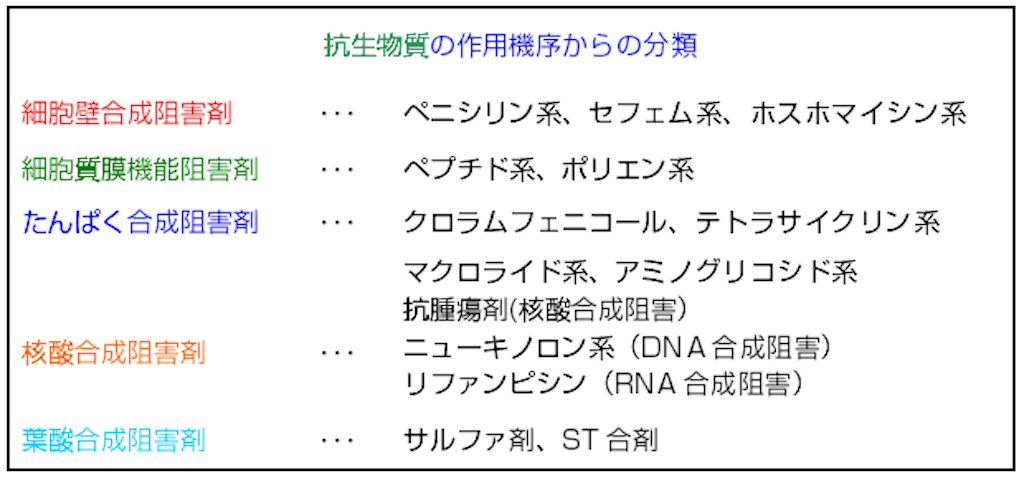
(https://www.hananoiyakkyoku.com/プライベートノート/抗生物質のチョコット知識/抗生物質のチョコット知識⑤/ より)
抗菌薬の機能を評価する指標としてPK/PD理論というものがある。PKとは薬物動態学・PDは薬力学のことである。薬物動態学は「生体に投与した薬物の体内動態」について研究する学問であるのに対し、薬力学は「薬理作用のメカニズム」を解析し研究する学問であると一般的にいわれている。薬物動態学・薬力学の二つを合わせた理論で抗菌薬の効果を検討するというのがPK/PD理論である。
この理論が生まれた背景として、抗菌薬の薬物動態の解析は以前より行われていたが、抗菌薬には上記した通り様々な作用が違う薬があり、濃度依存的に効果を示すもの、時間依存的に効果を示すものなどタイプによって評価基準がバラつくため、効果の予測には薬の血中濃度など薬物動態だけでは不十分である。
また細菌の薬に対する感受性や薬の移行性についても検討する必要性がある。そのため生まれたのがPK/PD理論であり、薬物動態学と薬力学を合わせることによって抗菌薬の有効性や安全性を評価することが可能となるのである。
PK/PD理論におけるパラメーターとして重要な項目がいくつかあり、PK(薬物動態)パラメーターとして重要なのは最高血中濃度(Cmax)と血中濃度曲線下面積(Area Under the Curve,AUC)であり、PD(薬力学)パラメーターとして重要なのは最小発育阻止濃度(MIC)だ。
Cmaxは薬剤を投与した後の最高の薬物血中濃度だ。要するに薬のピーク値だと考えていただければイメージしやすい。
AUCとは、Cmaxを縦軸に濃度、横軸に時間となるようグラフ化したときの面積をAUCと定義される。少しわかりにくいがAUCが一体何を表しているのかというと、「どのくらいの濃度で、どのくらいの期間にわたり、薬が血中を循環したのか?」ということだ。
例えば、血中濃度が一気に上がっても、代謝が大きければ、血中から速く薬がなくなるのでAUCは小さくなる。一方、血中濃度の立ち上がりが遅くても、代謝能の小さい薬物であれば、血中に長く残ることになるため、AUCは大きくなる。 ざっと言えば、AUCは体内循環で流れた薬物の全体量をイメージして頂くとわかりやすいと思う。


(AUCの図。https://www.fizz-di.jp/archives/1036355660.htmlより)
PDパラメーターで重要な指標であるMICとは抗菌薬が細菌の発育を阻止するための最低の濃度のことを指す。つまり、MICが低いということは少量で殺菌できるということであり、それだけ効果が鋭いということだ。例えば、黄色ブドウ球菌に対するAという薬剤のMICが1、Bという薬剤のMICが2だった際に、より黄色ブドウ球菌に強い抗菌薬はAということになる。
これらのPKとPDのパラメーターを合わせたのがPK/PDパラメーターであり、%T>MIC(Time above MIC)、Cmax/MIC、AUC/MICというパラメーターから抗菌薬は評価される。
%T>MIC(Time above MIC)は 血中濃度がMICを超えている時間であり、時間依存性の抗菌薬の指標になる。細胞壁合成阻害剤のペニシリン系抗菌薬、βラクタム系抗菌薬は時間に依存して効果を発揮するため、こちらのパラメーターが評価指標となる。%T>MICを増やすには一回の投与量を増やすよりも投与回数を増やすことが有効であるため、一日複数回の投与が行われることが多い。つまり、如何に体内に長時間の抗菌薬の曝露をさせるのかというのが時間依存性の抗菌薬の治療目標となるのである。
Cmax/MICは濃度依存性タイプの薬物の作用と相関するパラメータであり、CmaxをMICで割った値である。濃度依存性は時間依存性と違い、組織に効果を発揮する十分な濃度が行き渡らないと効果発現が見込めないため、最高血中濃度(Cmax)と効果を発揮する指標である最小発育阻止濃度(MIC)を割ることによって、効果発現する濃度がどれだけの速さで移行するかを評価するのである。濃度依存性の抗菌薬において、体内での高いピーク濃度を達成させることが治療目標となる。濃度依存性の代表的な薬剤であるキノロン系の薬剤はこちらのパラメーターが指標となる。
AUC/MICはAUCをMICで割ることで求められる値であり、一般にCmaxとAUCは比例するのでAUC/MICを使用することも多い。つまり、AUC/MICも濃度依存性の抗菌薬の指標になるのだが、バンコマイシンなど時間依存性であるが、PAEという持続効果がある薬剤もあるため、AUC/MICを指標とすることがある。この辺りはhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/dermatol/122/7/122_1749/_pdfに詳しく記載されているため、ご興味のある方は一読頂きたい。
何が言いたいのかというと、抗菌薬には様々なメカニズムで効果を発揮する数々の種類があり、多くの種類があるが故に評価指標のパラメーターが多く存在し、種々のパラメーターから細菌に対する抗菌薬の強い・弱いなどを判断されているということだ。

では、抗ウイルス薬の作用機序はどうであろうか?ここで思い出して頂きたいのは、冒頭にて触れた細菌とウイルスでは全く別の“モノ”であるという点だ。細菌は細胞壁を持つのに対してウイルスは持たない。つまり、抗菌薬の作用機序はウイルスには効果が無いということだ。
また、ウイルスの進化は細胞を有する生物とは著しく異なり、個々のウイルスの形質の多様性は著しく高いとされている。そのため、それぞれに対する個別の治療薬が必要となることが多い。昨今、世間を騒がせている新型コロナウイルスの特効薬が出来ないのもこういった理由もあり、一朝一夕ですぐに抗ウイルス薬が出来るというわけではないのである。
抗ウイルス薬はそれぞれ個別の薬剤が必要と記したが、ここでは代表的なウイルスであるインフルエンザウイルスに対する抗ウイルス薬の作用メカニズムに関して触れることとする。
抗菌薬と同様に様々なメカニズムを持つ抗ウイルス薬が発売されているが、代表的なのはノイラミニダーゼ阻害薬であるタミフル、リレンザ。RNAポリメラーゼ阻害薬であるアビガン、キャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬であるゾフルーザといったところであろうか。
インフルエンザウイルスは細胞に侵入した後の増殖する過程において、必要なノイラミニダーゼという酵素が必要である。これを抑制することでインフルエンザウイルスを細胞内に閉じ込めることにより、増殖を抑えるというのがノイラミニダーざ阻害薬のメカニズムだ。しかし、ノイラミニダーゼを持たないC型インフルエンザには無効であるのが欠点である。
インフルエンザウイルスは細胞内に侵入した後、RNAという遺伝情報を細胞内へ放出し新たなウイルスを作り増殖していく。RNAポリメラーゼ阻害薬はこの遺伝情報のRNAを阻害するのである。
インフルエンザウイルスは細胞内に侵入した後にRNAという遺伝情報を放出すると記したが、このRNPはウイルスRNAの転写によるウイルスmRNAの合成と、ウイルスゲノムRNAの複製という作業をそれぞれ異なる手順によって行っている。このうち、mRNAにはキャップ依存性エンドヌクレアーゼという酵素が携わっていることが判明したため、キャップ依存性エンドヌクレアーゼの働きを阻害し、ウイルスのmRNA合成を阻害することで抗ウイルス作用をあらわす。これがキャップ依存性エンドヌクレアーゼ阻害薬である。

(https://www.data-index.co.jp/knowledge/detail4-2.htmlより)
ざっくり記しただけでも、抗菌薬と抗ウイルス薬のメカニズムの違い、菌とウイルスの違いが何となくおわかり頂けたかと思う。前置きが長々となってしまったが、ここからはアロマによる抗菌・抗ウイルス効果は果たしてあるのかということに関して触れていきたい。
(繰り返しになりますが、あくまで個人的な意見・見解であり、僕は完全に門外漢であるため、参考程度になれば幸いです)
アロマオイルは水蒸気蒸留法などによって植物から抽出する精油のことであり、古くから虫除け、香料また抗菌作用を期待して人類が活用していきた歴史がある。アロマオイルの抗菌効果に関してだが、川上らが2012年の発表した20種類の精油の微生物に対する制菌効果(https://jglobal.jst.go.jp/detail?JGLOBAL_ID=201202211107862500)によると、ティートリー、ラベンダーなどには細菌に対して制菌作用があると報告されている。


(ハロー法で調べた各種の精油の制菌作用。ハロー法の詳細はリンクを参考下さい。公益社団法人 日本アロマ環境協会より抜粋https://www.aromakankyo.or.jp/basics/literature/new/vol7.php )
また2017年に福岡県立大学からの報告によるとタイムレッドの精油が表皮ブドウ球菌に対して抗菌作用を有することも報告されているし(実用化に向けた精油の殺菌抗菌効果の解析 http://www.fukuoka-pu.ac.jp/academics/nurse/bulletin2/13_1pdf/13_1_75.pdf)、同大学からティートリー、ラベンダー、シナモンリーフの精油が大腸菌、表皮ブドウ球菌などに対して抗菌作用が確認されたことも報告されている。(ティートリーとラベンダーの抗菌効果の検討http://www.fukuoka-pu.ac.jp/academics/nurse/bulletin2/11_2pdf/11-2-4.pdf 、シナモンリーフ精油の殺菌抗菌効果の解析 https://fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=repository_action_common_download&item_id=120&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1&page_id=13&block_id=21)
また、海外でも同様の報告がされていることから、ある種類のアロマオイルは抗菌作用を有していることが示唆出来ると思う。
ただし、これらの報告では精油は原液では皮膚刺激性が高いため、希釈することが必要であるが、希釈により大幅に殺菌抗菌効果が下がることから、現時点では皮膚に対する消毒目的には適さないと結論されていることに目を向ける必要がある。
原著を読んでいただければご理解頂けると思うが、これらの報告は医療器具の消毒に精油を役立てるにはどれくらいの希釈濃度が適正なのかという部分がエンドポイントである。
また、どのような作用機序で精油が抗菌効果を示すのかということに触れられていない点にも注意が必要だ。この作用するメカニズムに関して紹介したいが、2001年に井上の報告によると抗菌作用の発現には芳香分子の吸着が必要であり、分子が吸着することにより菌糸の発育が阻止され、静菌・抗菌作用を発揮するとある。
精油の種類により抗菌活性の機序も違うみたいだが、膨大な量になるため割愛させて頂くけれども、詳しく知りたい方は下記の原著を確認して頂きたい。要するに、抗菌薬と精油では抗菌の作用機序が全く違うということだ。ちなみに、作用するメカニズムが違う点から精油は細菌の耐性化も生みにくいと推測されている(あくまでも推測)。

(精油の抗菌作用の機序のイメージ。https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/39/7/39_7_475/_pdfより)
では、精油の抗ウイルス効果は如何であろうか?1995年の研究によるとドクダミの精油は単純ヘルペスウイルス(HSV-1)、インフルエンザウイルスおよびHIVに対する活性が報告されている(VirucidalEffects of the Steam Distillate from Houttuynia cordataand its Components on HSV-1, Influenza Virus, and HIVhttps://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/s-2006-958063)。
また本邦にて2019年に発表された報告によるとマウスの吸入実験によりユーカリなど精油がインフルエンザウイルスの増殖を抑制することが明かになったとされている。(植物精油の直接接触および芳香暴露の抗インフルエンザウイルス作用に関する研究 https://ci.nii.ac.jp/naid/40016607681 )。以上のことから、ある特定の種類の精油には抗菌作用に加えて抗ウイルス作用を有するものもあることが示唆される。
ただし、これらの報告で注意する点がある。それは、人体における皮膚による経皮吸収や鼻粘膜や口腔内による吸収での精油の薬物動態が全く検討されていない点だ。
なぜこの部分が重要な課題かというと、ロウリュした際でのアロマオイルの吸収は蒸気と共にサウナ室へ漂うため、口腔での吸入・鼻粘膜・経皮吸収が主となる。そのため、ヒトでの口腔吸入・粘膜吸収・経皮吸収での体内動態が検討されていないと、ロウリュに使用した際に効果があるかどうかが判断できないのである。
ヒトにおける経皮吸収のメカニズムとして、角層への移行→角層での透過と広がり→角層から表皮(角層以外)への分配→真皮以下の各組織における分配および拡散という複雑な過程にわけられる。また薬の角層への移行に影響を与える因子として、角層水分量や基剤と皮膚との接着性、薬物の分子量など、これもまた複雑な因子が挙げられる。
要するに、何が言いたいかというと経皮吸収でのアロマオイルの有効性を検討した報告は余りなされていないし、ロウリュに使う時点で希釈して使用しており、複雑なヒトの経皮吸収の過程を考えると経皮吸収から抗菌作用に有効な濃度の移行は期待出来ないことが推測されるということだ。
またロウリュ後にはほとんどの人が水風呂に入ると思うが、その時点で水で有効な成分が洗い流されている点が推測されるため、ロウリュのアロマに経皮吸収での効果を期待するのは難儀だろう。

(経皮吸収の過程のイメージ。https://www.maruho.co.jp/medical/penles_info/mizuibo/hifu/より)
では、鼻粘膜からの吸収(経鼻吸収)はどうだろうか?経口投与された薬物は大半は通常では小腸にて吸収され、血流に乗って標的部位に運ばれる前に肝臓に達するため、多くの薬は腸壁と肝臓で化学的に変化し、血流に乗った時点で薬の量は少なくなる。
一方、経鼻吸収されると小腸や肝臓を経由されることなく血流に入るため、一般にこのルートを通ると効果の発現が早いとされる。しかしながら、鼻粘膜は5~10μmと非常に薄いため、吸収のためには薬を極めて小さく、つまり霧状にする必要がある。鼻粘膜そのものを薬剤吸収のターゲットとした場合、10~50μ m のサイズが望ましいとされている。
しかし、ここで問題になるのが鼻粘膜のもつバリア機能である。鼻粘膜は粘膜線毛クリアランスとタイト結合という 2つのバリア機能を有しており、吸収促進作用が加えられていないと有効な濃度で薬剤が移行するのは困難であるとされる。
こういったバリア機能という障壁を乗り越え、作用したい箇所に的確に効果を発現出来るように製材化を工夫することをドラッグデリバリーシステム(DDS)と呼ぶ。言い方は悪いが、アロマオイルをただ水で希釈しただけで全くDDSが工夫されていないアロマ水がどれほど鼻粘膜を介して人体に吸収されるのかは想像に難くないと思う。

(鼻粘膜のバリア機能。https://www.jstage.jst.go.jp/article/orltokyo/51/Supplement/51_Supplement_s32/_pdf/-char/ja より)
また口からの吸入は鼻で吸い込む薬よりも分子をさらに小さくしなければならない。そうしないと薬は気管を通り抜けて肺まで到達しないからだ。薬が肺のどのくらいの深さまで届くかは大きさによって変わり、小さいほど深い所まで届き、薬が吸収される量が増えるとされる。さらに、この方法で薬を投与するには特殊な器具が必要で、例えば吸入器を用いる喘息薬などを想像して頂くとわかりやすいと思う。
つまり、口腔吸入に関してもDDSが考慮されていないアロマ水ではどれだけ体内に吸収されるのかは未知数である。(薬の動態に関してご興味のある方はhttps://www.msdmanuals.com/ja-jp/ホーム/02-薬について/薬の投与と薬物動態/薬の投与 をご覧下さい)
紹介した上記のインフルエンザウイルスでのアロマオイルの効果を検討した試験はin vivo(生体内での試験のこと)でも効果が認められたとあるが、マウスと人体での薬物動態は異なることが多いし、人体での薬物動態の検証がなされていない点からアロマオイルはヒトでも有効と簡単に結論付けて言えないのではないだろうか。
ここで冒頭に記したPK/PD理論を思い出していただきたい。これまでアロマオイルの抗菌効果・抗ウイルス効果を消化してきたが、その中において人体でのアロマオイルのCmaxやAUCの検討がなされていないという点がある。
実際にアロマオイルを入れたスチームなどでどれだけ体内へ有効な成分が移行するかなどはCmax/MICなどの指標を用いないと効果判定が出来ないし、アロマオイルは時間依存性に効果を発揮するのか・濃度依存性なのかというのも明確になっていないところだ(恐らく、作用機序を考えると濃度依存性だろうが、推測の域を超えない)。
PK/PD理論を用いた効果判定の報告を探してみたものの、ヒットしなかったため、まだまだ検討の余地は大いにあるということだろう。京都府立医大の今西氏の2004年に発表されたメディカル・アロマセラピーの総論にも“今後の課題として、できるかぎり質の高い臨床試験を目指すことが最優先であろう”と一文があるため(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcam/1/1/1_1_53/_pdf)、やはり臨床において科学的根拠が十分に有しているということは言い切れないのではないかだろうか。
昨今では、新型コロナウイルスが猛威を奮い、数々のエビデンスの無い療法の情報が錯綜している(お湯を飲めばウイルスが不活性化されるなど)状況であり、アロマによって新型コロナが不活性化するという情報も耳に入ることもある。
新型コロナウイルスに対するアロマオイルに関しての研究がはっきりと言って不十分であり、日本アロマセラピー学会でも「新型コロナウイルスに直接的な抗ウィルス作用を示したエビデンスは、当学会が知る限りではありません。したがって、現時点では、新型コロナウイルスに精油が有効であるとするには時期早尚であるとするのが、日本アロマセラピー学会の統一見解です」と記載されている。
つまりは、単純にアロマオイルの効能を過信してしまうのはよろしくないということである。

ここまで駄文・長文となってしまったが、最後にポイントをまとめることとする。
・細菌とウイルスは全く別のモノ
・抗菌薬には様々な作用メカニズムがあり、効果判定の指標としてPK/PD理論が用いられる
・抗ウイルス薬も同様に様々な作用メカニズムがあり、抗菌薬はウイルスには効果がない(細菌とウイルスは別のモノであるため)
・アロマオイルには抗菌作用・抗ウイルス作用を有する種類もある
・ただし、ヒトでの体内の薬物動態を考慮すると効果発現する濃度がちゃんと移行しているのかは大きな疑問が残る
・アロマを過信せずに付き合うのが無難
以上の点が、個人的な考察であり、これから少しでも多くの方々の参考になれば幸いである。
最後に予断だが、ラベンダーとティーツリーで男子の胸が女性化したとの報告がNEJMという非常に著名な学術誌に報告されているため、アロマオイルの副作用にもよく注意しながら使用していきたいものである。(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa064725)